
梅棹忠夫 関係2点
人類学者は草原に育つ
『Voice from Mongolia, 2020 vol.68』
事務局から
梅棹忠夫 生誕100年で光
民博で今秋企画展「知的生産」に焦点
京都市出身の民族学者、梅棹忠夫(1920~2010年)の生誕100年を13日に迎え る。没後10年の節目でもある今年は、梅棹の「知的生産」に焦点を当てた企画展が初代館 長をつとめた国立民族学博物館(大阪府吹田市)で今秋開催予定で、記念出版も相次いでいる。 世界文明を大胆に捉え直した「文明の生態史観」や情報社会への洞察といった「知の探検家」 の見方は、コロナ渦で揺れる今だからこそ存在感を増している。(樺山聡)
「常に知的生産のフロントランナーだった」 民博での展示「知的生産のフロンティア」(9月3日~10月20日)を企画する小長谷有紀・ 民博客員教授はそう指摘する。 文明の盛衰を気候や地理条件から生態学的に解明して1957年に発表した「文明の生態史 観」では日本文明は西欧の模倣でなく平行に進化したと唱え、62年発表の「情報産業論」 でポスト近代にコンテンツが産業の中心になるといち早く予測したことなどを、小長谷客員 教授は挙げる。 「インターネット時代の今では当たり前に使われる『知的生産』という言葉の生みの親も、 まぎれもなく梅棹」という。
69年に出版された「知的生産の技術」(岩波新書)は今も人気が衰えず重版を続け、岩波 書店によると今年100刷に至った。
この本は梅棹が「まえがき」で言うように「知的生産」を編み出すコツを解説するような、 いわゆる「ハウ・ツーもの」ではない。
「コロナ渦越えるヒントに」
梅棹は同書で「かんがえることによる生産」である「知的生産」が、研究や報道、出版と いった限られた分野だけでなく幅広い人々にとって重要になると指摘。自らがフィールドワ ークで得た情報を論文にまとめる上で磨いた方法論を説き明かしている。
その中に「こざね」という聞き慣れない言葉が登場する。ある主題で文章を書く際に、折 に触れ記した着想メモなど関係のある事柄をまとめていく。その連なりを、鎧の小札に例え て梅棹はそう名付けた。
秋に民博で開催予定の企画展では、そうした情報を加工する過程が分かる梅棹の手帳やカ ード、「こざね」、写真などをデジタルアーアイブを使って紹介する。小長谷客員教授は「イ ンターネット時代の今だからこそ、梅棹が手作業で実践した知的生産の方法論は示唆に富む。 多くの著作を残した舞台裏を体感できる内容にしたい」と話す。
大きな節目の年にあわせ、司馬遼太郎との対談を収録して2000年に出版された「日本 の未来へ」(NHK 出版)の新装版が、臨川書店(左京区)から3月に復刊された。
また、淡交社(北区)が1969年から最終巻として梅棹を執筆者として企画されながら、 多忙などで実現しなかった幻の著書「日本人の宗教」が同社から5月に出版された。民博の 梅棹資料室に残された約350枚の「こざね」を基に宗教学者の中牧弘允・民博名誉教授が 推薦して筆した。 「実にユニークな視点で、日本の宗教を文明史的に考察しようとしていた」 中牧名誉教授は語る。 「教義と信仰者の関係をメーカーとユーザーに例え、メーカーである教義の側から捉えた従 来の宗教史ではなく、特定宗教に熱心でない一般の人々への聞き取りも通してユーザー側の 視点で捉え直そうとした」
刊行は立ち消えになったかにみえた著書が没後10年に「後継者」の手によって完成した ことは、「こざね」の持つ大きな力をしめした。
生誕100年という大きな節目を新型ウイルスが世界的に席巻する今、梅棹が挑んだ「知 の冒険」は何を語りかけるのか。
中牧名誉教授は「マクロに文明史を見つめた先見性や、人類の抱える未来の不安を予知し て政策的に一つ一つつぶすという考え方は、試練を超える手掛かりをくれるだろう」と話す。 =敬称略
(2020年6月10日京都新聞朝刊に掲載された記事)
半歩遅れの読書術
没後10年 梅棹忠夫の先見性 意外な切り口で人々を扇動
(小長谷 有紀・文化人類学者)
「太陽の塔」がみどりのなかに突き出ている公園。それは、1970年に大阪万博が開催 された博物館であり、そこに国立民族学博物館はある。その創設に奮迅し、長らく館長を務 めた梅棹忠夫(1920年~2010年)は、つねに意外な切り口で人々を扇動し続けた思想 家であった。
54年、『思想の科学』にアマチュア思想家宣言を寄稿し、カメラのように思想を使いこ なそうと提案した。57年には『中央公論』で「文明の生態史観序説」を発表し、文明の復 線的な展開という考え方を提示した。それは同時にね日本をヨーロッパと対等に「辺境」と 位置付ける図式の提案でもあったから、西欧に没頭しがちな日本人を根源的に鼓舞すること にもなった。
59年には『婦人公論』に「妻無用論」を執筆し、女性の社会進出を鼓舞した。「女たちは 爆発する」という声援は、時代を先取りしすぎていたため、妻たちには不詳なぐらいだった。 63年の「情報産業論」は、情報ということばがスパイ用語だった時代に、8ビットパソコ ンでさえまだ日本に登場していない時代に、機器よりもコンテンツが産業を牽引すると予測 した。そして、そんな風に世界を先読みする技法のコツを、69年の岩波新書『知的生産の 技術』で人々に惜しげもなく提供した。
20年はそんな梅棹忠夫の生誕100年かつ没後10年にあたる。節目を記念する展示が 国立民族学博物館で4月に行われる予定であった。コロナ渦により延期され、今のところ9 月3日からの予定である。小さな企画展なので図録は用意されていない。企画者の一人とし て、私のお勧めは、『知的先駆者の軌跡 梅棹忠夫』(千里文化財団)である。亡くなって翌年 の追悼展示「ウメサオタダオ展」のために作られ、このたび再版された。まさに古くて新し い本だ。かって、急遽実施することになった展示のために、多くの関係者が膨大なエネルギ ーを集中的に投下した。その価値は今後もさがるまい。
梅棹本人の著作の中でどれがお勧めかと、もし問われたら、私の答えは決まっている。難しいですと即答は避けたい。何が響くかは人それぞれなので、回答は代えて、最新作2点を ご紹介する。一つは『梅棹忠夫の「日本人の宗教」』(淡交社)。残されていた執筆構想が再現 されている。もう一つは『日本の未来へー司馬遼太郎との対話』(臨川書店)新装版である。 ポストコロナ時代の生き方のコツも、きっと含まれているに違いない。
(6月5日 日経新聞に掲載記事)
小長谷 有紀著 人類学者は草原に育つ変貌するモンゴルとともに
(臨川書店フィールドワーク選書)9
小長谷 有紀著
第二章 はじめてのフィールドワーク ―1988年、中国内モンゴルでの研修
ふるさとの名はバヤンノール「豊かな湖」
私がはじめてフィールドワークをしたのは、中国内モンゴル自治区シ リンホト市の郊外であった。はじめてのゲル(中国語で包と呼ばれるモ ンゴル人の移動式住居)にホームスティをした。1988年3月のこと である。
2013年10月、久しぶりにその地を訪れた。シリンホト市内から 舗装道路を北上し、そこから草原に入る。しばらく走って、小高い場所 から、私のお世話になっていた人びとの暮らす一帯を展望することができる。

ああ、いいところだなあ。
ゆるやかな起伏があって、盆地というほどではないが、四方を囲まれているいちばん北側 に見えるのが私の住まわせていただいた本家で、南側に親戚たちが散らばっている。
最初にここにやってきたとき、私は何もわかっていなかった。ここは本当にいいところだ ということを、いまわかっているような感じでは、わかっていなかった。この四半世紀のあ いだ、あちらこちらを走り、そこかしこを歩き、そしてようやくいまにいたって、ここは本 当にいいところだ、とわかる。自然環境ばかりでなく、町からわずか一時間ほどの距離にあ るという社会環境も含めて。
「ほんとうにいいところだねぇ」と、運転席のウネルバヤンに告げると、彼は「父が選ん だ場所だからね」と答えた。彼は、私のホームスティ先の末息子である。
ここでは末子(ばっし)相続のしきたりがまもられている。きょうだいの上から順に、女な ら婚出し、男なら独立し、次々と立ち去り、そして最後に残った息子が家督を継ぐ、という しきたりがある。立ち去ることのできる者から順に立ち去っていくという規則は、過度な放 牧を避けることができて、いかにも合理的である。遊牧世界に適した社会制度であると思わ れる。
父のダンゼンは南のチャハル地方から移住してきた。母のツェベルマーは北のダリガンガ 地方から移住してきた。このあたりに親戚などはいなかった彼らは、「好きな場所を選んで住 んだだけだよ」とウネルバヤンは解説する。
ウネルバヤンのきょうだいは10人いる。そのうち、2人の姉と1人の弟は養子にだされ た。一方、1人の兄は養子として迎え入れられた。このように養子の出入りの多いのは、モ ンゴルではごくふつうのことである。ただし、当時は気づかなかったが、いまならもっとわ かる。なぜ、養子の出入りが多いのか。
母が生んだ最初の子ども4人は女ばかりだった。そして、たまたま、姪が結婚するとき、 彼女が婚前に産んでいた子をひきとった。それは男の子だった。連れ子をひきとってあげる ことによって、実は、男の子が欲しいという願望を直裁的に実現することができる。そして また同時に、そうすることで男の子に恵まれると母は考えたにちがいない。
モンゴルでは子どもが子どもを連れてくると考えられていて、養子を迎えるのは、実子に恵まれんがためである。めでたく実子がうまれても、けっして養子をないがしろにはしない。 なぜなら、その養子こそが実子をもたらした源泉だと考えられているからである。こうした 考え方は、実子が生まれたあとでも養子をないがしろにしない文化的装置になっていると思 われる。
実際のところ、ウネルバヤンの母は男の子の養子をもらってから、再婚したあと4人の男 の子にめぐまれた。最後の息子が生まれたときはすでに40歳を超えていて、産後の肥立ち が悪かったこともあって、子どもに恵まれない実の娘に養子に出した。つまり、娘の養子に することによって、実子は孫になった。だから、彼女には、先にもらった養子を含めて、後 に養子に出した子を除いて4人の息子がいる。 1988年当時、下の3人の息子たちが母のそばに住んでいた。上から順に遠くへ独立して いて、残る3人のうち、1人目はおよそ2キロ南側にいた。2人目はすぐ近く東にいた。3 人目は西隣にいた。これが末子で家督を継ぐウネルバヤンである。
はじめてフィールドワークに来たときは、いろいろ事実をきくだけで精一杯である。まず、 人の名前を知り、関係を教えてもらう。それだけでノートの書き込みがいっぱいになるから、 何ほどかのことがわかったような気になる。しかし、それは知っただけのことで、分かった わけでなかったことを、いまようやくわかるような気がする。
あのときは、はじめてのフィールドワークだから、私にとってこうした養子縁組の実例は まさに初耳だった。その後、4半世紀のあいだに、あらゆる家庭でそうした養子縁組の実例 を聞くこととなった。とくべつにそれを研究テーマにするわけでなく、話の糸口として子ど もたちのことなら比較的に聞きやすいから聞く、そのうち、養子縁組について豊富な実例が 私の頭のなかでどんどん蓄積されていた。だから、いまならわかる。否、わかるような気が する。単に事実としただけでなく、男の子を授かりたいという願いがみごとに実現されたの だなあと推測することができる。
何もわからない私に、とりあえずわかったような気にさせてくれ、そしてやがて本当にわ かるようになるための道を開いてくれた場所、その名をバヤンノール「豊かな湖」という。 研究者としての私のふるさとである。
老夫婦の写真
ダンゼン一家の宿営地にかつては、4つのゲルが並びたち、西から2つ目の一番大きなゲ ルが本家で、その東西に二人の息子が住み分けていた。末の息子が跡取りだから、本家の一 部とみなされる。大きなゲルとその西隣のゲルという二つが本家であり、東側の二つが次男 ウルジーチンゲルの家であった。
2013年に再訪すると、もっとはっきり両家は分けられるようになっていた。そのあい だに鉄線の囲いがもうけられているので、まるで仲違いでもしたかのように見える。生産請 負制に移行してから、放牧地は各世帯に分配されるようになり、さらにそれぞれ鉄線で囲う という政策が実施された。南に住む長兄リンチェンドルジはこのあたりの地区長をしていた から、その弟たちなら当然、積極的に政策を実行にうつさなければならなかったにちがいな い。
かつて自由に往来できた両家のあいだには、金網が張られ、そのうえ、それぞれの敷地で 固定家屋が建てられている。あのころすでに、ゲルを移動させることはあまりなく、実質的 に定住していたが、決して固定家屋ではなかった。固定的な建築物としては、せいぜい、西 北側の台所と東北側の物置しかなかった。それらはいまでもそのままあり、建物の陰に隠れ てとても小さく見える。
それにもまして変化したのは、家畜囲いだ。かつて4つのゲルからなる両家は、それぞれ の家畜群を統合し、放牧していた。そうすることによって労働力の合理化をはたしていた。 というのも、ヒツジ、ヤギの群れなら、100頭放牧するのも300頭放牧するのも同じで ある。おおよそ1000頭をめどに、群れは統合される。たとえば、もし500頭ずつ群れ を統合すれば、一家の主要な働き手は2日に一度放牧に出ればよい。残りの一日は他の仕事 ができる。あるいは、ウシやウマの群れの担当というように分担することもできる。放牧という仕事の場合、協業というのはかならずしも連れだって同じ場所に出て一緒に働くことで なく、交代ないし、分担を意味する。
ところが、現在は金網で分けられた宿営地に、それぞれ別の家畜囲いが建っている。それ も大きな固定施設が。どうやら、いまでは群れを統合することもないらしい。いつかまたゆ っくり聞き取りをしてみたい。
このたびはお線香をあげるためにやって来た。本家の父ダンセンは、2004年に86歳 で他界し、母ツェベルマーは2012年に92歳で他界した。このふるさとの両親の死に、 私は致命的に間に合わなかった。
本家の跡継ぎウネルバヤンのすまいは固定家屋になっていた。台所にはかって天幕の中心 に置いて火を起こし鍋をのせていた「五徳」が残されていた。西側に置かれた仏壇は、東側 を向いていて、そこに父母の遺影が飾られている。とても懐かしい。なぜなら、それは、盛 装した老夫婦を私が撮影した写真そっくりだからである。1988年当時、父は70歳、母 は67歳であった。その写真は『季刊民族学』50号(1989年)に掲載されており、その 雑誌をかつて差し上げた。すると、父は、「こうして私たちは歴史になるのだな」と感慨深げ に語った。
遺影に向かって手をあわせていると、仏壇に置かれいいた数珠をウネルバヤンの妻セルゲ レンが渡してくれた。「姉さんが来るのを待っていた」と言う。姉さんというのは私のことで ある。形見分けであった。それは母が肌身離さず持っていた数珠であり、一仕事終わればい つも何気なく、繰っていた数珠であった。
ぼんやりと思い出す。母はそれを兄の形見だと言っていた。いまならよくわかる。兄がラ マ僧だったこともあって彼らは難を避けて南へ逃げてきた「仏のいる土地へ行こう」と母の 家族が決意をしたのも、ラマ僧になった息子が革命政権によって逮捕されたり、殺されたり しないようにという想いがあったにちがいない。その大切な兄の形見を母は私に残してくれ たのだった。
中国内モンゴル社会科学院への留学
1988年春におこなった、はじめてのフィールドワークについて、すでに『モンゴルの 春』(河出書房新社、1991年)で紹介した。日記風にまとめているので臨場感もある。と 思う。フィールドワークの楽しさはその本で伝わるだろう。ぜひ読んでほしい。現在、みん ぱくのホームページの機関リポジトリのコーナーに公開されているから、無料でダウンロー ドすることができる。古本ではあるが、存外、古くはないかもしれない。先に述べたように、 現場はすっかり変わってしまった。けれども、はじめて出会う人びととの交感のプロセスと しては、決して古びているわけではない。
そこに書いていなかったことを、ここに記しておこう。そもそもなぜ、ここヘフィールド ワークに行くことができたのか?
1986年4月、私は京都大学文学部の助手になった。まさに男女雇用機会均等法が施行 されたときである。私はこの法律の誕生と同時に職に就いた。文学部の助手という職におい て、男女の差はあまりなかったが、学科による差は大きかった。同僚の一人は、助手となる なり、「自分が助手の時は研究室の雑用を言いつけられてたいへんだったから、自分も仕返し してやる」と助教授に言われそうである。教養ある知識人とはとても思えない上司をもった 同僚は気の毒だった。私はそんないじめを受けることもなくすんだが、ただ、たしかに雑用 は本当に多かった。学生たちの面倒をみるのは当然としても、研究室で購入した書籍が数年 分もたまっていて、それら一冊ずつすべてに図書ラベルを貼る仕事などは残っていた。毎日 本をあげさげしているうちに(もちろん読む暇はない)、ついに立てないほどの腰痛になった りもした。
モンゴルへの思いは、留学期間を一年に切り上げて帰国して以来、とりあえず封じておく しかなかった。何しろ、モンゴル人民共和国はソ連の傘下にあり、そのソ連と中国は対立し たままである。モンゴルはもはやあきらめたほうがよいかもしれない。牧畜民の研究を続け るために、調査先をアフリカに転じようかと、実際にどの地域へ調査に入るかもほぼ決まっていた。ところが、そのころ、京都大学人文学研究所東方部の杉山正明先生が中国での研究
を終えて帰国され、中国内モンゴル社会学科学院のジョロンガ先生の手紙を持ち帰られた。
そこには、内モンゴルで実態調査ができるという旨が書かれていた。そのことを私は同じく
人文研の谷泰先生を通じて知る。
文化大革命が終結してそろそろ10年になろうとしていた。中国における外国人による調 査研究も許可されるようになっていた。内モンゴルと日本人のあいだには現代史における因 縁があるから、中国側の様子をよく見なければうかつに現地調査などできない。それでも、 現地の知識人がもう大丈夫だと言うのである。
のちに知ったことだが、ジョロンガ先生は、建国大学の出身であった。それは、日本が中 国を植民地として支配しようとしていた時代、まさに日本側の幹部として養成されたことを 意味していた。だからきっと文化大革命では相当に厳しく罰せられたにちがいない。そんな 人が、もう来ても大丈夫だと言うのだから、それは相当に大丈夫であるらしかった。とりあ えず、内モンゴルでの調査研究は開放されたのである。
そして、5月にみんぱくへ。大学の助手から博物館の助手へという移動は、一見、格下げ に見えるので反対される向きもあったらしい。そこで、私の恩師であり上司でもあった応地 利明先生は、本人のためであるいうことを力説してくださったと聞いている。
こうして無事にみんぱくに異動すると、文部省(当時)の在外研究が募集されていた。一般 にここの費用を用いて研究者は欧米へ行き、研鑽を積むものだが、私はこの費用でフィール ドワークをと願った。もちろん、研修先は、中国内モンゴル社会科学院であり、受入者はジ ョロンガ先生である。

無事に機関から申請することができ、さらに採用されて、12月から10ケ月の予定で中 国に赴くとことができた。みんぱくにはわずか半年しかいないで、少々慣れたかなと思うこ ろに、いったん離れるわけである。そんなわがままが許されたことに深く感謝する。あの1 0ケ月がなければフィールドワークもなかった。研究上のふる さとと出会うこともなかった。あの10ケ月はそして、後述す る梅棹忠夫著作集の編集作業にとっても、非常に有益であった。
それにしても、全体にとても急いでことをすすめていた感じ がする。やはり、研究上「春」の観察が決定的に必要だったか らである。春に研究所に留学いていたらとても間に合わない。 年内に留学し、そこからフィールドワークを申請し、春に現場 にいるようにするために逆算して、おそらく書類の処理を最速 にしてもらってつかんだタイミングだっただろうと思う。
『Voice from Mongolia, 2020 vol.68』
(会員 小林志歩=フリーランスライター)
「何千年も昔から家畜とともに暮らして来た民族だから…。」
ダルハン出身、技能実習生(35)
北海道は牧草刈りのシーズン真っ盛りである。牛にたっぷりの乳を出させるために欠か せない、栄養価の高い「一番草」を刈る大型機械が、広々とした草地でフル稼働している。 北海道牛乳、と聞けば、緑の牧場やサイロのある風景を思い浮かべる人が多いと思うが、そ の生産現場が外国人技能実習生に支えられていることをご存じだろうか。中国やベトナム、 そして近年はモンゴル人も見かけるようになった。
初めて外国人実習生を受け入れたある牧場に、モンゴル人実習生を訪ねたときのこと。若 いスタッフは「牛舎に初めて入ったときから、牛たちの列に臆することなく近づいていった のはさすが」と感心していた。牧場での初仕事となれば、日本人ならまず牛の大きさに圧倒され、緊張せず、牛の側で作業できるまでにはいくらか時間がかかるだろう。 街育ちでも、長い夏休みには地方の草原に滞在し、田舎の親戚に交じって家畜の世話に関 わって育つことが多いからかな、と問いかけた際に、実習生から返って来たのが冒頭のひと ことである。しっかり者の彼女は、幼い子どもを残して来日して1年半になる。牧場になく てはならない存在という。「将来は学んだことを生かしてモンゴルで牧場経営に携わるのが 夢」だそうで、日本にいるうちに協力者を見つけたいと日本語学習にも意欲的に取り組んでいる。
モンゴルで ISO 認証を取得した食品工場で働いていた B さんは、衛生面の細かい作業指示の理解も早く、ほどなく搾乳作業をまかされるようになったが、だれもがそんなにスムーズ
に認められるわけではない。牛乳の衛生基準が高い日本では、搾乳の際には細心の注意を払
うことが欠かせない。細かい作業手順がなかなか頭に入らず、すべきことを忘れる実習生も
いる。何度も叱る経営者も、理解がままならない外国語で怒られる実習生も、双方にストレ
スがたまる。
実習生たちの働く牧場は、百頭前後から数百頭までさまざまだが、「牛舎のなかでにつなが れて多くの時間を過ごす牛が何だかかわいとそう」「日本人が牛の糞をすごく汚ないものとと らえていることに驚いた」…。率直な感想のひとつひとつに、文化の違いが浮かび上がる。
日本で酪農が始められたのは、渡来人の系譜を感じずにいられない古代の「蘇」を別にす れば、幕末から明治の近代化にかけてだから2百年にもならない。太平洋戦争後の学校給食 導入で牛乳を飲むことが一般的になり、機械化と規模を拡大することで生産量を増やし続け て現在に至っている。
規模を拡大する、つまり頭数を増やすということは、補助金を活用し、莫大な借金を背負 って、大型の牛舎や搾乳施設を導入することを意味する。働き手の確保が困難であるため、 何億円もする搾乳ロボットも導入され始めている。酪農家というより、牛乳生産工場の様相 である。対照的に、放牧でコストを抑え、小規模でも収益性が高い酪農経営を展開する牧場 もある。
モンゴル高原では紀元前から乳を搾り続けて来て、20世紀後半には旧ソ連の指導で近代 的な大規模搾乳場が稼働していた。社会主義の崩壊で昔ながらの遊牧風景に戻ったが、集約 的な農場も増えている。現代っ子の彼らは、どんな技術を祖国に持ち帰りたいと思うのだろ うか。
タンチョウヅルの群れがやって来る、海岸近くの牧場で働く実習生の O さんは、草原のゲ ルで育った。自家消費用に分けてもらう搾りたての牛乳で、ヨーグルトやウルム(加熱、攪 拌して乳脂肪を分離した伝統的な乳製品)を作り始めた。「ウルムをためておき、トス(ウル ムを加熱し、砂糖やレーズンを加えた甘いお菓子)を作るの」と嬉しそうに話してくれた。 北海道牛乳で作ったツァガーン・イデーの味が楽しみである。
(会員・フリーランスライター 小林志歩)
************************************************************************************
今月の気になる記事
この春出会った技能実習生のひとりは、モンゴルの西部ホブド県の「ザハチン」と出自を 語った。国境を守る役割を担っていたことがその名の由来とか。モンゴル国の周辺、国境近 くの草原には、多くの少数民族(モンゴル語でウンデステン)が暮らす。
司馬遼太郎が『草原の記』(新潮社、1992年)で紹介した通訳のブリヤート人女性ツェ ベクマさん(1924 – 2004)は、まさに国境地帯に生まれ育ち、国家にがんじがら めにされつつ、強い意志で境界を越えて生き抜いた人。その自伝『星の草原に帰らん』(NHK 出版、1999年)によって、直接逢えなかった彼女の人となりに触れることができた。よ くぞこの人生を記しておいて下さった、と著者はもとより、出版を企画・実現した日本人関 係者に感謝せずにいられない。戦前の「満蒙」とそこに生きたモンゴル人、日本人の生きざ まを今に伝える本だ。
今回は、ウェブで見つけたブリヤートの伝統についての記事をお送りする。事実上の国境 閉鎖が明けたら、東部の草原を訪ねてみたい。
М.ナムジルマー「私たちブリヤート族は、1年生の子どもでも先祖9代まで言える」 (筆者:S.オヤンガ)
系譜を知ることがなぜ必要かを理解しない人は多い。知ろうとも、注意を払おうともしな いことにより、モンゴルの少数民族は、血縁が近いものが結婚する危険性に直面することを、 研究者が確認している。その見立てによると、9代以内で親戚が結ばれるのは危険である。 9代以上のことであれば、外部の人と見なすことができる。9代どころか、2-3世代さか のぼれば、誰かわからない人もいるといっても過言でない昨今だが、ブリヤート族は幼い子 どもでさえも系譜を知っているという。ブリヤートの人々を代表し、マハバダル・ナムジル マーを招いて話を聞いた。 「私たちのソムでは、そこらで遊んでいる6歳の子供に聞いても先祖9代の名を言える」。ド ルノド県ダシバルバルソムで長年教員を務めた M.ナムジルマーは、現在11代までさかのぼ る家系図を受け継いでいる。この驚くべき女性を、政治・ニュースのウェブサイト《ネグ・ ウドゥル Нэг Өдөр》欄で取材した。
父は、モンゴル文字で記した家系図を残した
M.ナムジルマーは、先祖代々の家系図を受け継いでいる。父親は、1940年頃から綴 り始めた家系図を子どもたちに残したという。ナムジルマーは、ダシバルバルソム、ドルノ ド県で、40年以上にわたり教壇に立った。 「私の知る限り、父は20歳くらいの頃に読み書きを習得したようです。手書きの縦文字で びっしりと書き込んだノートが手元にあります。姉と私が引き継いで書き続け、今では11 代目に入っています。当初は自分の家族について記すだけでしたが、その後、どこの家も家 系図を記すべきだと考えるようになりました。ソムの人たちに教える中で、家系図を作る際 の見本となる書式を作成しました。昔は父方についてのみ綴っていたのですが、70年代以 降は母方についても記録しています。
姉も私も教員でした。はじめの授業で子どもたちに『家系って知ってる?』と質問したも のです。知らない場合は、両親から聞いて書いて来るように言っていました。一般に、ブリ ヤート族の伝統として、だれもが学校に上がる頃には9代さかのぼって言えるようになった ものです。家に遊びに来た近所の子どもにも必ず、家系を尋ねる習わしがあります。言えた らキャンディや果物、乳製品をごほうびにあげます。知らない場合は、聞いておいで、と言 って帰らせたものです。
地元の子供たちは皆9代前まで言えます。低学年から伝統について学校の授業で教えてい ますから。系譜を知るために9代より前についても書き出させて、親戚についても覚えさせ ます。ダシバルバルソムでは、外で走り回っている子どもの誰に聞いても、9代さかのぼる ことができます。
うちの家系は11代まで判明しています。2013年に家系図を製本し、親戚や子供たち、 孫に配布して、親族にどのような人がいたのかを理解できるようにしました。10年たった らまた本を出したいと思います。わが家は5人子どもがいますが、家系図は長男が継承する ことにしています。
当初は、家系図を月と太陽の形式で書いてみましたが、紙の上に収まりそうもなかったの です。行の形で書いたところ、1頁に多くの名前が収まりました。父、母、自分、子供たち の世代を、横に分類してゆきます。例えば、私の父はドルゴシ・ガルゾード氏族であり、母 方はノホイ・オラグ・フグドゥード氏族に属していました。
11代さかのぼると、シャル・チョノ、その次の代はハル・チョノといいます。9代にわ たり氏族内で結婚しないという伝統を厳格に守っています。かつては、氏族の間で「ハタグ を置く」(婚約する)ことがよくあったようです。氏族を尋ね、灯明を燃やし、ハタグを受け 取らずに帰したものでした。今はこうしたことは見かけませんが、別の見方をすれば、家系 図をつけていない、系譜が明らかでないことによる、とも言えます。婚約を取り決めるにあたっては系譜を紹介する習慣を持つべきです」。
うちの家系に4人の戦士がいた
ナムジルマーの氏族の祖はバルガバータルでした。彼女の祖父は、バルガバータルの3人 の妻のひとり、ホリルダイの子孫とみられています。11代のうちにドルゴシ・ガルゾード 氏族は5百世帯を超え、千人近い大家族を成しています。
家系図を記すだけでなく、特徴的な人物についての事績を後世に伝えることにも取り組ん でいます。
「家系図を見る限り、母方の4人の兄は戦に出かけました。活躍した人物について子ども たちに伝えるため、人物像について記述しています。
最近、4か月あまりかけて関係省庁や情報機関の文書館で調査をし、伯父たちが戦争に行 った証拠書類を入手し、家系図に添付しました。最も若かった伯父は、西部国境の紛争に参 加していました。ほかにも、国家表彰の牧民や労働英雄もいます。資料を現在登録してもら っており、調査を続けています。
研究者の先生方と議論した中に、外国人と結婚した人たちをどのように扱うかという件が ありました。わがソムから外国人と結婚する人も少なくないものですから。そうした人々も 家系図に記録すべきです。当人も子どもも、モンゴルの国民なのですから」
ダシバルバルでは、家系図を記録していない家はありません。ナムジルマーとお姉さんは 自らの家系図を記すことにとどまらず、県や村に働きかけ、1991年以降はすべての家庭 で家系図を熱心に記すようになっています。子どもたちは学校に上がる時に、自分が誰の子 どもであり、どの氏族に属しているかを質問し、中学年になると、伝統や産業、生活につい ての授業の中で、家系図の大切さを教えているそうです。氏族内での婚姻が許されないこと、 祖先を敬い、祀るとともに、よく知ることが重要であると伝えています。
「研究者は、チンギスに続く40代まで調査をしています。これにうちの家系の11世代を 加えれば、50代余りを明らかにしたことになります。家系を知らないことにより、モンゴ ルの少数民族に何らかの悪影響が出ている可能性が研究者 によって叫ばれています。 近縁の結婚により、様々な欠陥や知的障害、思考力のない子どもが生まれています。今後さ らに深刻になれば、民族が滅亡する危険性を問うた英国の研究もあります。このことからも、 家系図の重要性について国民が理解する必要があります。政治による後押しも重要です」。
ナムジルマーは、業績が評価されて首都での引退生活を送っていますが、教え子のコンク ール出場の指導等のため県やソムに戻ることも多く、家系図作成の講座を開くなど、普及活 動を続けている。 「ゾーニーメデー」紙より転載
ニュースサイト http://www.polit.mn/a/75325 2019年11月22日
(原文モンゴル語) (記事セレクト・訳=小林 志歩)
※転載はおことわりいたします。引用の際は、必ず原典をご確認ください。
斎藤様 とても興味深い記事に感謝です。+小長谷先生の記事は面白くこんな良い時代があったのですね。志歩さんの記事は考えさせられることが多かったです。(吉崎 彰一)
今月も面白いですね。小長谷先生の連載も最高です。 サロールさんの絵は本当に素晴らしいです。夜空の絵は国立国際美術館所蔵の作品(作者の名 前を思い出せません)を彷彿とさせるできばえです。これからどんな展開をしていくのか、楽 しみです。(金田 悦二)
(モピ通信216号に対していただいたものです)
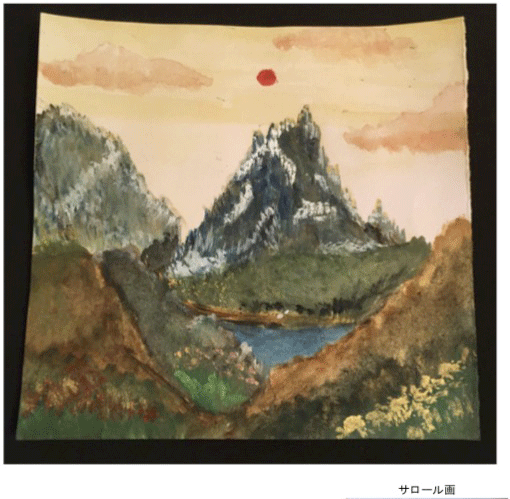
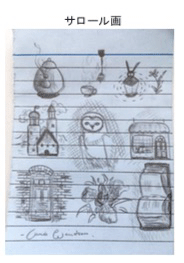
事務局からお知らせ
ながいコロナ時間が過ぎました。いろいろな意味で 自分を振りかえる事ができる時間でもありました。
新年度がスタートしてこれという動きがないまま、 夏休みを迎えます。次号218号は、9月1日付けの 発送になります。小長谷先生のコラムなど紹介できる と思います。ご期待ください。
モピ年会費収めていただいた皆さま、ありがとうご ざいました。未納のみなさま、よろしくお願い申し上 げます。
(斎藤 生々)
************************************************************************************
特定非営利活動法人 モンゴルパートナーシップ研究所/MoPI
〒617-0826 京都府長岡京市開田 3-4-35
tel&fax 075-201-6430
e-mail: mopi@leto.eonet.ne.jp
URL http://mongolpartnership.com/
編集責任者 斉藤生
************************************************************************************
